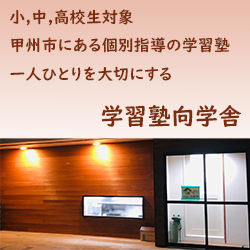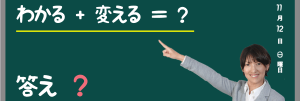R7年3月定例会での一般質問:甲州市の財政規模について
3月定例会での一般質問についてまとめました。
R7年甲州市一般会計当初予算案では、歳入歳出ともに過去最大の208億円が提案されています。
そこで、甲州市の財政状況について、以下の3つの観点から考え、質問をしました。
①甲州市の標準財政規模
②甲州市の中長期財政推計との乖離
③甲州市の行政コスト
①甲州市の標準財政規模
まず、答弁によると甲州市の標準財政規模は、R6年度では104億円でした。
(標準財政規模とは、標準的な状態で通常収入されるであろう、経常的一般財源の規模を示すもので、通常水準の行政サービスに必要な一般財源の目安となるものです。地方税、地方譲与税、標準税収額と普通交付税と臨時財政対策債発行可能額がこれらに含まれます。)
H31年に廣瀬宗勝議員が質問された際の答弁では、甲州市の標準財政規模は100億円前後で推移しているとのことでした。それから7年経過していますが、現在の甲州市の標準財政規模にはそれほど大きな変化があるとはいえません。
一般会計予算が膨らんだ主な要因は、国の政策による人件費(1億1700万円、約5.4%増)、児童手当等(1億5600万円、約45.5%増)、PCB処理を含む橋梁長寿命化、環境センター跡地広場整備事業費など普通建設費(4億2500万円、約32.6%増)によるそうです。
過去最大となった歳入歳出はどこからその財源を確保して、事業を行うのか、次の観点から考察をしていきました。
②甲州市の中長期財政推計との乖離
甲州市の中長期財政推計は、R4年2月に見直しが行われたばかりですが、推計では、R7年は歳入歳出ともに164億円余としています。当初予算208億円との乖離についてどのように考えているのか問いました。
推計との乖離については、ふるさと納税を10億円と見込んでいることと、児童手当の拡充など国の政策が反映されていないことが要因にあるそうです。また、中長期財政推計の主眼は財政収支や基金、地方債残高等の傾向を把握するためのものであり、地方債は概ね推計に沿っているとのことでした。私もグラフを作って比較してみましたが、甲州市の市債の状況は見事に推計と一致しています。
推計でも予定通り進んでいる、むしろ「ふるさと納税」や「基金残高」は上振れしているので、甲州市の財政状況は改善し、良い状態になっているのかと仮説を立ててみましたが、そうでもないようです。
私が初当選したころは、甲州市の財政状況は、市債の償還(返済)のピークを迎えたこともあり、大変厳しかったです。当初予算編成の際にも、どの課においても一律5~10%カットという話も毎年のように聞いていました。
R7年度の予算編成においては、昨年6月定例会の補正予算を上限に設定し、厳しく予算査定が行われたそうです。しかしながら、予算案をみると、新規事業も散見されるので、予算がだいぶ潤沢にあるのかという印象を受けました。
そこで、次の観点からも財政状況を考えてみました。
③甲州市の行政コスト
決算のデータになりますが、甲州市の行政コストはR5年度は180億7035万7683円でした。
(行政コストとは、現金主義会計を補完する民間企業の会計手法の発生主義、複式簿記の考えであり、新地方公会計制度に基づく資料です。損益計算書に相当する行政コスト計算書から求めることができます。資産形成以外の行政サービス等にかかる人件費や物件費、退職手当引当金繰入金、減価償却費を含むフルコストで計算されています。)
この行政コストを賄うための財源確保は大きな課題です。甲州市はふるさと納税が好調であることも背景に、純行政コストを上回る財源確保ができている状態ですが、それも大きく上回っているとは言えないので、ふるさと納税頼みの予算編成になっていることは言うまでもありません。
今後、人口減少が見込まれている甲州市としては、現在のように要望があれば、それに応えるというような政策を次々と実行できるような状態ではないということもできます。
現在、甲州市の財政状況を一言で表すと、将来世代が負担すべきところを現役世代が負担するという形になっています。受益者負担の考えから、行政では将来世代が利益を享受するものは、その世代も負担すべきという考え方があり、多くの事業で市債(借金)を充当して事業を行っています。
毎年生まれてくる子どもたちの数を鑑みれば、将来の人口が今よりも少なくなることは、簡単に誰でも予測できることです。将来世代へとなんでも先送りしてしまうやり方に、どこかで終止符をうっていかなければならいと私は考えます。